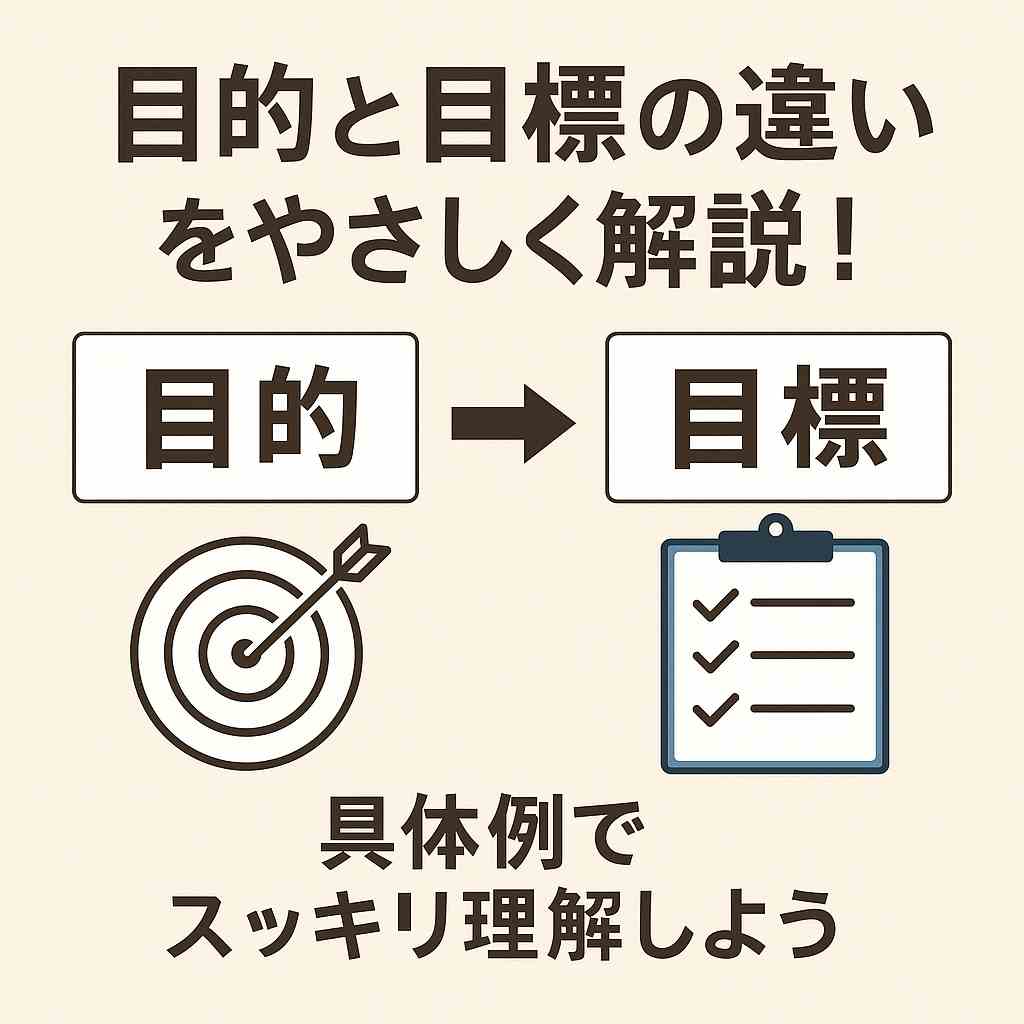目的と目標の違いとは?
目的とは「最終的に成し遂げたいこと」
「目的」という言葉は、私たちが何かを始めるときに一番大切な“出発点”になります。簡単に言えば、目的とは「最終的にどうなりたいか」「何のために行動するのか」を示すものです。
例えば、あなたが勉強を始めるとしましょう。「大学に合格すること」が目的であれば、それは最終的に到達したいゴールです。このとき、目的は単なる行動の一部ではなく、人生や日常の中で大きな方向性を示すものとなります。
もう少し広い視点で考えると、「自分の可能性を広げたい」「社会で役に立てる人になりたい」といった価値観や思いも目的の一つです。つまり、目的は「行動の理由」であり、「原動力」なのです。
また、目的は時間の経過に左右されにくい特徴があります。一度「なりたい自分」や「達成したい姿」が定まると、それは長い時間をかけてでも追いかける価値のあるものです。たとえ途中で失敗しても、目的さえぶれなければ再び立ち上がることができます。この「変わりにくさ」も目的の大きな特徴です。
目標とは「目的に近づくための通過点」
一方で「目標」とは、目的を達成するための具体的なステップや基準を指します。目的が大きなゴールだとすれば、目標はその道のりに置かれた「チェックポイント」と言えるでしょう。
例えば、「大学に合格する」という目的を掲げたとします。そのための目標は「模試で偏差値60を取る」「1日3時間勉強する」「数学の教科書を3ヶ月で1周する」といった具体的な行動や数値です。
つまり、目標は「実際に行動できる形」にまで落とし込まれたもの。数値や期限があることが多く、進み具合を確認できるのが特徴です。
目標は小さく設定することも、大きく設定することも可能です。しかし、目的と違って「短期的」であることが多く、状況によって柔軟に変える必要があります。例えば、模試の成績が思うように上がらなければ「1日2時間の復習を増やす」というように、目標を修正するのです。
このように、目標は「現実的に行動できる基準」であり、目的にたどり着くための道しるべとなります。
なぜ混同されやすいのか
多くの人が「目的」と「目標」を混同してしまうのは、どちらも「達成したいこと」として表現されるためです。しかし、よく考えてみると違いが見えてきます。
例えば、会社の研修で「売上を上げることが目的です」と言われる場合があります。でも実際には「売上を上げる」は目標に近い表現です。本来の目的は「会社を成長させる」「お客様に価値を提供する」といったもっと大きな方向性であるべきなのです。
このように、言葉の使い分けが曖昧になると、目標が目的のように扱われてしまい、「何のためにやっているのか」が見えにくくなります。
さらに、「目的」と「目標」は人によって定義の仕方が異なることも、混乱を生む原因です。ある人は「資格を取ること」を目的と呼び、別の人はそれを目標と呼びます。正解が一つではない分、どう区別すればいいかが分かりにくいのです。
しかし、シンプルに整理すると次のように覚えることができます。
| 言葉 | 意味 | 特徴 | 例 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 最終的に成し遂げたいこと | 抽象的・長期的・変わりにくい | 大学に合格する/社会で役立つ人になる |
| 目標 | 目的を達成するための具体的な通過点 | 具体的・短期的・柔軟に変えられる | 模試で偏差値60を取る/1日3時間勉強する |
この表を意識すると、「目的=ゴール」「目標=チェックポイント」とイメージしやすくなります。どちらも大切ですが、順番を間違えると努力が空回りしてしまうこともあるので注意が必要です。
目的と目標を区別するメリット
達成イメージが明確になる
目的と目標をきちんと区別する最大のメリットは、「自分がどこに向かっているのか」がはっきり見えることです。
目的がぼんやりしていると、どれだけ目標を立てても「それを達成した先に何があるのか」がわからず、達成感ややりがいを感じにくくなってしまいます。逆に、目的を先に明確にすれば、目標は「そのための道筋」として位置づけられるため、行動の意味がぐっと理解しやすくなるのです。
例えば、「健康になりたい」という目的を持った人がいるとしましょう。目的だけでは漠然としていて、「健康になるってどういうこと?」と迷ってしまうかもしれません。そこで、「1日30分ウォーキングをする」「野菜を毎日2皿食べる」といった具体的な目標を設定すると、目的が目に見える形でイメージできるようになります。
目的を大きな「ゴール」とし、目標を「小さな道しるべ」に分けることで、やるべきことが一目でわかるようになるのです。
この「見える化」は特に長期的な取り組みに効果的です。勉強、ダイエット、資格取得、仕事のプロジェクトなど、すぐに成果が出ないものは途中で投げ出してしまいやすいですが、目的と目標を分けておけば、進んでいる実感を持ちながら取り組むことができます。
努力の方向性がブレにくくなる
目的と目標を混同してしまうと、途中で「何のためにやっているんだろう」と迷子になることがあります。
例えば、受験勉強をしているときに「模試でいい点を取る」ことだけが頭にあると、本来の「志望校に合格する」という目的を忘れてしまいがちです。その結果、模試の点数だけを追いかけてしまい、合格に必要な勉強とのバランスを崩してしまうこともあります。
このように、目標にばかり意識が向くと本来の目的から外れてしまうのです。
一方で、目的を明確に持っていれば、「この勉強は合格のために必要だ」「この練習は本番で力を発揮するためだ」と、自分の努力の意味を再確認できます。
目的がコンパスの役割を果たし、目標が地図上のチェックポイントになるイメージです。目的を常に意識することで、進むべき方向を見失わずに行動できるのです。
また、社会人の場合も同じです。会社で「売上を伸ばす」という目標を追いかけるだけでは、社員のモチベーションは長続きしません。しかし「お客様に喜んでもらえる商品を提供する」という目的が共有されていれば、売上という目標がそのための手段だと理解でき、仕事に誇りを持って取り組めます。
計画が立てやすくなる
目的と目標を分けて考えると、計画を立てやすくなるのも大きなメリットです。
目的が「最終的なゴール」、目標が「そのためのステップ」と位置づけられるため、自然と「逆算思考」ができるようになります。
例えば「英語を話せるようになりたい」という目的があったとします。その場合、目標を「TOEICで600点を取る」「海外ドラマを字幕なしで理解する」と設定し、そのために「毎日英単語を30個覚える」「週に1回オンライン英会話を受ける」とさらに細分化していけば、日々の行動計画に落とし込めるのです。
逆に、目的と目標を混同すると、計画が「その場しのぎ」になりがちです。「とりあえず今日やること」だけを考えるため、全体の流れが見えずに行き詰まってしまうことがあります。
しかし目的をしっかり意識していれば、「今週はこの目標をクリアすればゴールに近づける」というように、長期計画と短期計画をつなげることができるのです。
この考え方は、学校の勉強やスポーツだけでなく、ビジネスやプライベートでも役立ちます。例えば貯金をするときも、「老後に安心して暮らす」という目的を持てば、「毎月3万円貯金する」という目標を立てやすくなります。そして、毎月の小さな積み重ねが最終的な安心につながるのです。
まとめ
ここまで見てきたように、目的と目標を区別すると次のようなメリットがあります。
- 自分が進むべき方向がはっきり見える
- 努力の意味を見失わずに続けられる
- 長期的なゴールに向けて計画的に動ける
つまり、目的と目標を正しく区別することは、「迷わず努力を積み重ねるための基盤」になるのです。
どちらか一方だけでは不十分で、両方をセットで考えることで最大の効果が得られます。
目的と目標の具体例でイメージしよう
勉強における目的と目標の違い
勉強は、目的と目標の違いを考えるのにとてもわかりやすい題材です。
例えば、中学生が「志望校に合格する」という思いを持っているとします。これは最終的にたどり着きたい場所であり、目的です。
しかし、目的だけでは行動につながりにくいですよね。「合格したい」と思っても、毎日何をすればいいのかがわからなければ勉強が進みません。そこで出てくるのが目標です。
「模試で数学の点数を20点伸ばす」「1日30分は英単語を暗記する」「テスト前に過去問を3回解く」といった具体的な数値や期限を設けるのが目標です。
つまり、目的は「合格」、目標は「合格に近づくための小さなステップ」と整理できるのです。
さらに、大学受験を例に取るとわかりやすいです。大学に合格するという目的のために、「TOEIC600点を取る」「数学ⅠAを3ヶ月で仕上げる」「模試で志望校判定をB判定に上げる」といった目標を設定します。これらの目標がクリアされるごとに、目的に一歩ずつ近づいていくのです。
このように勉強では、目的=最終ゴール、目標=日々の勉強の指針という形で使い分けると、迷わず進むことができます。
仕事における目的と目標の違い
社会人にとっても目的と目標の区別は非常に大切です。
例えば、営業職の人が「売上を伸ばす」という言葉をよく使います。しかし、本来の目的は「会社を成長させる」「お客様に満足してもらう」「チーム全体の成果を高める」といったもっと大きなものです。
そのうえで「今月の契約件数を20件にする」「新規顧客を5社開拓する」「リピート率を80%にする」といった具体的な数値を目標として設定します。
目的が「お客様に価値を提供する」なのに、目標が「売上を上げる」だけになってしまうと、やり方が無理な営業になったり、短期的な利益だけを追いかけたりする危険性があります。逆に、目的を常に意識していれば、目標の意味がはっきりし、成果が出やすくなります。
例えば、新しいサービスを開発するプロジェクトでは、「人々の暮らしを便利にする」という目的があるとしましょう。そのための目標は「3ヶ月以内に試作品を完成させる」「ユーザー調査を100人に実施する」といった具体的なタスクになります。
目的を忘れずに行動すれば、短期的な数字だけでなく、本当に社会に役立つサービスを生み出すことができるのです。
スポーツにおける目的と目標の違い
スポーツの世界でも、目的と目標を分けて考えることは重要です。
例えばサッカー部に所属している高校生の場合、「全国大会に出場する」というのが目的になります。これはチーム全体で共有する最終的なゴールです。
そのための目標としては、「今月の練習試合で5勝する」「1日100本のシュート練習をする」「ランニングタイムを10分縮める」といった具体的なものが考えられます。
目的を「全国大会出場」に置くことで、練習がつらいときも「この努力は大きなゴールにつながるんだ」と思えます。そして、日々の目標を達成するたびに「少しずつ目的に近づいている」という実感が持てるのです。
また、個人競技でも同じです。マラソンランナーにとって「フルマラソンを完走する」が目的なら、「週に30km走る」「タイムを5分縮める」というのが目標です。目的と目標を分けて考えることで、計画的にトレーニングができ、途中で心が折れるのを防ぐことができます。
身近な例をさらに考えてみよう
勉強・仕事・スポーツ以外でも、日常生活には目的と目標の違いを意識できる場面がたくさんあります。
例えばダイエットの場合、目的は「健康的な体を手に入れる」「好きな服を着こなす」などです。それに対して目標は「1ヶ月で体重を2kg減らす」「毎日20分ウォーキングをする」といった行動レベルのものです。
旅行でも同じです。目的は「リフレッシュして心を癒す」ことであり、目標は「1日で3つの観光地を回る」「現地の料理を2種類食べる」といった具体的な計画になります。
どんな場面でも共通するのは、「目的はゴール、目標はそこに行くためのステップ」ということです。この視点を持つだけで、日常生活のあらゆることが整理しやすくなり、達成感も味わいやすくなります。
目的と目標をうまく設定する方法
SMARTの法則を活用する
目標を立てるときに役立つフレームワークとして有名なのがSMARTの法則です。これは以下の5つの頭文字をとったもので、達成しやすい目標を作るためのポイントを示しています。
- S(Specific:具体的であること)
目標は「何を」「どのように」と明確にしましょう。例えば「勉強を頑張る」ではなく「1日30分英単語を暗記する」とすることで、実際の行動に直結します。 - M(Measurable:測定可能であること)
成果を数値や基準で測れるようにすると、進捗が確認できます。例えば「模試の偏差値を60にする」「体重を2kg減らす」など、数値化できる目標はやる気を維持しやすいです。 - A(Achievable:達成可能であること)
高すぎる目標は挫折の原因になります。少し頑張れば届くレベルに設定するのがポイントです。「1週間で10kg痩せる」は非現実的ですが、「1ヶ月で2kg痩せる」は現実的です。 - R(Relevant:目的に関連していること)
設定した目標が、本来の目的とつながっているかを確認しましょう。「英会話を上達させたい」という目的に対して、「歴史の本を10冊読む」という目標は関連性が薄いですよね。 - T(Time-bound:期限があること)
期限のない目標は、いつまでも先延ばしにされてしまいます。「3ヶ月でTOEIC600点を目指す」といったように期限を設定することで、行動にスピード感が生まれます。
このようにSMARTの法則を意識して目標を設定すれば、漠然とした思いを具体的な行動に変えることができます。
そして、その目標をクリアしていくことで、最終的な目的達成への道筋が自然と見えてくるのです。
長期的な視点と短期的な視点を組み合わせる
目的と目標を設定するうえで大切なのが、長期的な視点と短期的な視点のバランスです。
目的は多くの場合、数ヶ月〜数年かけて達成するものです。例えば「大学に合格する」「海外で働けるようになる」「健康的な体を手に入れる」といった目的は、すぐに達成できるものではありません。
そのため、長期的な目的だけを見ていると「遠すぎて実感が湧かない」「途中で諦めてしまう」ということが起きます。そこで必要なのが短期的な目標です。
「今週は単語帳を100個覚える」「1ヶ月で3kg減らす」「来月までに資料作成スキルを習得する」といった短期目標を立てることで、日常の行動に落とし込めるのです。
逆に、短期目標だけを積み重ねても「そもそも何のために頑張っているのか」という目的がなければ、方向性を見失ってしまいます。
長期目的=人生やキャリアのコンパス、短期目標=毎日の行動の地図として両方を組み合わせることが大切です。
目的と目標を紙に書いて整理する
頭の中だけで目的と目標を考えていると、どうしても曖昧になってしまいます。そんなときは紙に書き出して整理するのがおすすめです。
例えば次のようなシンプルな表を作ると、目的と目標の関係がひと目でわかります。
| 目的 | 目標 |
|---|---|
| 英語を使って海外で働く | TOEIC800点を取る/オンライン英会話を週3回受講する |
| 健康的な体を手に入れる | 週3回ランニングをする/1日野菜を200g以上食べる |
| 大学合格 | 模試で偏差値65以上/1日4時間勉強 |
このように書き出すことで「自分は何のために努力しているのか」「そのためにどんな行動をすべきか」が明確になります。
さらに、紙に書いたものを机や手帳に貼っておけば、モチベーションを維持しやすくなるという効果もあります。
まとめ
目的と目標をうまく設定するためには、次の3つを意識すると効果的です。
- SMARTの法則を取り入れて、達成しやすい目標を立てる
- 長期的な目的と短期的な目標を組み合わせて考える
- 紙に書いて整理し、見える形で確認できるようにする
これらを実践することで、漠然とした思いが具体的な行動計画に変わり、目的に向かって着実に進めるようになるのです。
目的と目標が混ざってしまったときの対処法
言葉にして確認する
目的と目標がごちゃごちゃになってしまう一番の原因は、頭の中だけで考えているからです。
そこでまず試してほしいのが「言葉にしてみる」ことです。自分の考えていることを声に出したり、ノートに書いたりするだけで、驚くほど整理されていきます。
例えば「資格を取ることが目的」と思っている場合、それを言葉にしてみると「本当に資格取得自体が目的なのか?」と気づけるかもしれません。多くの場合、「資格を取ってキャリアを広げたい」「自分に自信をつけたい」というように、資格取得は目的ではなく手段(目標)であることが見えてきます。
また、書き出す際には次のように分類するとわかりやすいです。
- これは「最終的にどうなりたいか」=目的
- これは「そのために今やること」=目標
こうして言葉に落とし込むことで、「あ、これは目的だった」「これは目標だ」と自分で納得しやすくなるのです。
他人に説明してみる
頭の中で整理できないときは、誰かに説明してみるのも効果的です。友達、家族、同僚などに「自分の目的と目標はこうなんだ」と話してみると、聞いてくれた人から「それは目標じゃなくて目的じゃない?」とフィードバックが返ってくることがあります。
他人に説明することで、自分が曖昧にしていた部分がはっきり見えてくるのです。
例えば、ダイエットをしている人が「毎日体重を測るのが目的」と話したとします。すると相手から「体重を測るのは目標じゃない? 本当の目的は痩せることや健康になることだよね」と指摘されるかもしれません。
このように、他人の視点を借りることで、自分では気づけなかった混乱を整理できるのです。
もし周りに相談できる人がいない場合は、自分が他人に説明しているつもりで紙に書き出す方法もおすすめです。文章にすることで、目的と目標の境界が自然と見えてきます。
振り返りと修正を繰り返す
目的と目標を一度整理しても、時間が経つとまた混ざってしまうことがあります。これは自然なことです。なぜなら、状況や自分の考え方が変わるからです。
例えば、就職活動のときに「大企業に入ること」が目的だと思っていても、実際に働き始めると「やりがいを持って働くこと」が本当の目的だと気づくことがあります。そのとき「大企業に入る」は目標に過ぎなかった、と見直せるのです。
そこで大事なのが定期的に振り返る習慣です。週に一度、月に一度など、自分の行動を振り返って「これは目的? 目標?」と確認しましょう。そして必要があれば修正してください。
修正することは決して悪いことではありません。むしろ柔軟に見直すことで、自分の成長に合わせたより良い目的や目標が作れるのです。
例えば、スポーツ選手が「全国大会で優勝する」という目的を持っていたとします。しかし怪我をしたことで「最後まで試合を楽しむ」ことが新しい目的になるかもしれません。その場合、練習メニューや短期的な目標も変える必要が出てきます。
このように、目的や目標は固定的なものではなく、状況に合わせて調整できるのです。
まとめ
目的と目標が混ざってしまったときの対処法を整理すると、次の3つがポイントです。
- 言葉にして書き出し、目的と目標を分類する
- 他人に説明してフィードバックをもらう
- 定期的に振り返って柔軟に修正する
これらを意識すれば、たとえ最初に混乱していても徐々に整理できるようになります。
大切なのは「目的と目標はいつでも見直していい」という考え方です。完璧を求めすぎず、成長に合わせて調整していけば、努力は必ず実を結んでいきます。
日常生活での活かし方
勉強や資格取得での活用
勉強や資格取得の場面は、目的と目標の違いを意識しやすい代表例です。
例えば「資格試験に合格する」というのは目的ではなく目標であることが多いのです。本当の目的は「キャリアアップをして収入を安定させたい」「専門知識を身につけて自信を持ちたい」といったもっと広いゴールにあるはずです。
資格合格そのものを最終目的とすると、合格後に「燃え尽き症候群」になってしまう人も少なくありません。
逆に、目的をしっかり意識していれば、目標設定がぶれません。たとえば「海外で働きたい」という目的があるなら、「TOEIC800点を取る」「英会話を週3回続ける」という目標は自然と出てきます。
勉強はどうしても単調になりやすいですが、目的を意識しつつ目標を積み上げることで「この努力が将来につながっている」と実感でき、モチベーションを維持できます。
さらに、目標を細かく区切るのも効果的です。「今月はテキストを1冊終える」「来週は模試を1回受ける」といった短期目標を設定し、それをクリアするたびに達成感を得ることで、最終目的に少しずつ近づいていることを実感できます。
仕事のキャリア形成での活用
社会人にとって目的と目標の違いを理解することは、キャリア形成に直結します。
例えば「出世する」「年収を上げる」というのは目標です。本当の目的は「家族との生活を安定させたい」「社会に貢献できる人材になりたい」「自分の能力を最大限に活かしたい」といったもっと広い価値観や生き方の方向性にあります。
目的を見失うと、昇進や給与だけを追いかける形になり、仕事が苦しくなってしまうこともあります。
逆に、目的を明確にすれば「自分がなぜこの仕事をしているのか」が見え、短期的な目標も納得感を持って取り組めます。例えば「社会に役立つサービスを作る」という目的があれば、「プロジェクトを期限内に完成させる」「新しい技術を半年で習得する」といった目標に意味が生まれます。
目的がモチベーションを生み、目標が行動を導くのです。
また、キャリア形成においては長期的な目的と短期的な目標を組み合わせることが大切です。例えば「10年後に独立して自分の会社を持ちたい」という目的があれば、「3年以内にマネジメントを経験する」「5年以内に営業スキルを磨く」といった目標を設定できます。
このように逆算して目標を作れば、キャリアの道筋が見えてきます。
趣味やスポーツでの活用
趣味やスポーツも、目的と目標の違いを意識すると楽しみ方が変わります。
例えば「マラソン大会に出場する」というのは目標です。本当の目的は「体力をつけて健康を維持する」「新しいことに挑戦して自分を成長させたい」「仲間と達成感を共有したい」などにあるでしょう。
目的を意識していれば、大会に出場できなかったとしても練習の時間自体が価値あるものになります。
スポーツに限らず趣味も同じです。例えば「ギターを弾けるようになる」という目標を立てたとしても、本当の目的は「音楽を楽しむ」「自己表現の幅を広げる」「仲間と一緒に演奏する楽しさを味わう」ことかもしれません。
目的を忘れてしまうと「うまく弾けない」と落ち込んでしまいますが、目的を思い出せば「楽しめているならそれでいい」と前向きに続けられます。
家庭や人間関係での活用
家庭や人間関係においても、目的と目標の違いを意識することは大切です。
例えば「家族旅行に行く」というのは目標ですが、本当の目的は「家族の思い出を作る」「一緒に過ごす時間を大切にする」といったもっと深いものです。
この目的を意識することで、旅行そのものよりも「一緒に楽しむこと」「会話を増やすこと」に価値を見いだせます。
人間関係でも同じです。「週に1回友達と会う」というのは目標ですが、その目的は「友情を深める」「安心できる関係を築く」ことです。
目的を忘れてしまうと、ただ回数をこなすだけの付き合いになってしまいかねません。目的を意識すれば、短い時間でも心のつながりを深められます。
まとめ
日常生活における「目的と目標の違い」を整理すると、次のようになります。
- 勉強や資格取得では「合格」より「その後の自分の姿」に目的を置く
- キャリア形成では「昇進」より「どんな働き方をしたいか」を目的にする
- 趣味やスポーツでは「大会や技術」より「楽しむこと・成長すること」に焦点を当てる
- 家庭や人間関係では「イベント」より「大切な人との絆」に価値を置く
目的は人生の方向性を示すもの、目標はそのための小さなステップ。この視点を日常生活に取り入れるだけで、行動に意味が生まれ、毎日が充実したものになります。
よくある質問(Q&A)
Q1: 目的と目標はどちらを先に考えた方がいい?
結論から言うと、目的を先に考えるのがおすすめです。
なぜなら、目的がなければどんな目標を立てても意味を見失ってしまうからです。例えば「毎日3時間勉強する」という目標を立てても、「何のために勉強するのか」という目的がなければ、途中で「どうして頑張っているんだろう」と迷ってしまいます。
目的は大きなゴールであり、進むべき方向を示すコンパスのような存在です。その方向性が定まれば、目標は「そのための具体的なステップ」として自然に決まってきます。
例えば「海外で働きたい」という目的を設定すれば、「TOEIC800点を取る」「英会話を週3回続ける」といった目標が明確になります。
ただし、最初から完璧な目的を見つける必要はありません。まずは「とりあえずこの方向で頑張ってみたい」という思いで十分です。その中で行動を積み重ね、目標を達成していくうちに「自分が本当に大切にしたい目的」が見えてくることもあります。
目的と目標は一度決めたら固定するものではなく、行動を通じて育っていくものと考えるとよいでしょう。
Q2: 目標を達成しても目的を見失うことはある?
はい、実際によくあることです。例えば「資格を取る」ことを目的だと思って頑張っていた人が、合格した途端に「これから何をすればいいのかわからない」と感じるケースがあります。これは、実際には資格取得が目的ではなく目標だったために起こる現象です。
目的と目標を混同していると、このように達成感の後に虚しさを感じやすくなります。
ではどうすればよいかというと、常に「その先にある目的」を意識することです。例えば「資格を取る」という目標の先には「キャリアアップして自分の可能性を広げる」という目的があるはずです。その目的を意識すれば、合格後も次のステップに自然と進めます。
同じことは仕事やスポーツにも当てはまります。例えば「大会で優勝する」という目標を達成した後に燃え尽きてしまう人もいますが、その場合「自分の成長を続けたい」「チームで協力する喜びを味わいたい」といった目的を思い出すことで、次のチャレンジにつなげられるのです。
目標は達成して終わりではなく、目的につながる道しるべ。そう考えると、達成後の迷いを防ぐことができます。
Q3: 目的や目標が途中で変わってもいい?
もちろん構いません。むしろ、変わるのが自然です。
人の考え方や価値観は、経験や環境によって常に変化していきます。学生のときに「いい大学に入ること」が目的だった人も、社会人になれば「自分に合った働き方を見つける」が目的に変わるかもしれません。
変化を恐れる必要はなく、「今の自分にとって大切な目的」を選び直すことこそ成長の証です。
例えば、スポーツを続けている人が怪我をしたとします。当初の目的は「全国大会で優勝する」だったかもしれませんが、怪我をきっかけに「最後まで競技を楽しむ」「後輩を育てる」と目的が変わることもあります。
このとき、目標もそれに合わせて変える必要があります。以前は「タイムを縮める」が目標だったかもしれませんが、今は「週に3回ストレッチをする」といった形に変えるのです。
大切なのは「目的や目標は柔軟に変えていい」と知っておくことです。変わるたびに「自分はブレている」と感じる人もいますが、実際にはブレているのではなく進化しているのです。
自分の成長に合わせて目的や目標を見直すことは、前に進むためにとても大切なことです。
まとめ
ここで紹介したQ&Aを振り返ると、次のように整理できます。
- 目的を先に考えると、目標が自然に定まる
- 目標を達成しても、目的を見失わなければ次に進める
- 目的や目標は変わってもよく、それは成長の証である
目的と目標の違いを理解するだけでなく、実際に生活の中で活かすときには「柔軟さ」も忘れないようにしましょう。
そうすることで、どんな状況でも前向きに努力を続けることができます。